手仕事が生む、唯一無二の精度
更新日:コラム

― 図面だけでは生まれないもの ―
家づくりにおいて「精度」と聞くと、多くの人はミリ単位の寸法誤差や、施工の正確さを思い浮かべるかもしれません。
しかし、私たちが大切にしている精度は、それだけではありません。
本当の精度とは、
“図面では測れない部分まできちんとつくれること”
だと考えています。
⸻
■ 図面の線は、職人の手で初めて「現実」になる
どれだけ緻密な図面を描いても、現場で木が反ることもあれば、
湿度で素材が微妙に動くこともあります。
紙の上の線は「理想形」でしかない。
その理想を、限りなく正確に、そして美しく“現実に移し替える力”——
そこに、手仕事ならではの精度があります。
寸法を守るだけでは届かない領域。
職人が木の癖を読み、道具の重さを感じ取り、
「この角度なら、美しくおさまる」という判断を積み重ねる。
その感性の連続が、図面以上の仕上がりを生みます。
⸻
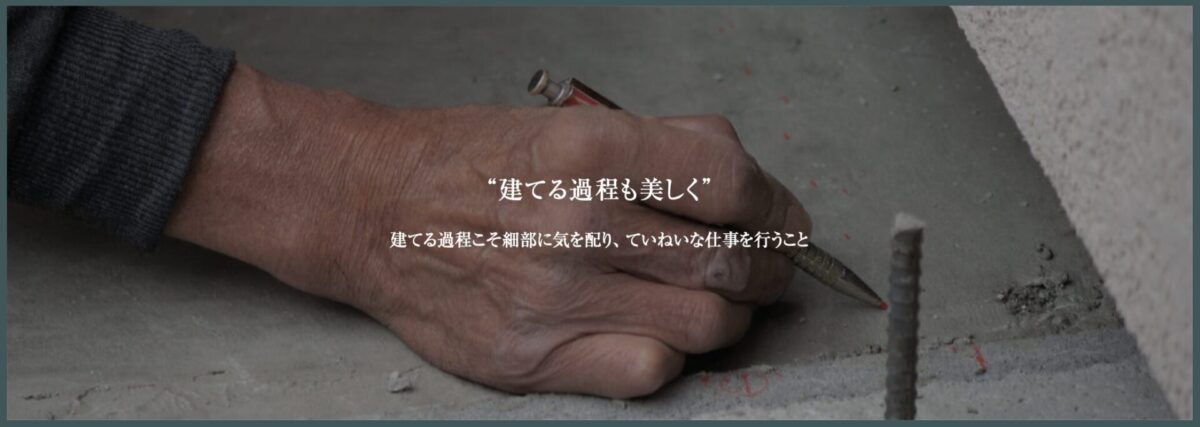
■ 手でつくるからこそ、誤魔化しが利かない
大量生産の材料は、見た目が均一です。
一方で私たちが使う無垢の木や左官、石、鉄は、全部表情が違う。
だからこそ、
“素材に合わせた精度” が求められます。
木の節の位置で表情が変わる。
左官のコテ跡ひとつで陰影が変わる。
鉄の溶接の温度で仕上がりのニュアンスが変わる。
どれだけ図面を完璧にしても、
最後は“手”が誤魔化せない世界です。
だからこそ、現場に立つ職人と密に話しながら、
ひとつひとつの納まりを丁寧に積み上げていきます。
⸻
■ 手仕事の精度は、20年後に証明される
精度の高さは、完成直後ではわかりません。
本当にその建物が“正しくつくられたか”は、
むしろ 10年後、20年後に現れます。
たとえば、
・無垢の木が反っていないか
・左官の壁が自然に呼吸しているか
・金物が歪まずに機能しているか
これらは、素材の性質を理解したうえで
最初の工事を丁寧に行っているかどうかで決まります。
手仕事の精度とは、
“未来に向けた誠実さ” なのです。
⸻
■ 機械ではつくれない精度がある
もちろん、機械の力が必要な場面もあります。
ただ、最も重要な部分——家の印象や使い心地を左右する部分は、
どうしても“人の手”に委ねられます。
私たちは、
・木の杢目を読み、最も美しく見える向きを探す
・壁の端部の線を揃えるために、数ミリ単位で調整する
・光が当たったとき、影が乱れないように面を整える
こうした、人にしかできない精度を積み重ねています。
それは、機械では再現できない“唯一無二の美しさ”をつくります。
⸻
■ 手でつくるから、長く付き合える
手仕事でつくられた家は、
あとから直したり手を加えたりしやすいという利点もあります。
量産品は、修理より交換のほうが早いことが多い。
でも私たちが選ぶ素材は、
20年後も、職人の手でちゃんと直せるもの。
これは“手仕事の精度”があって初めて成立します。
直せる家は、長く大事にされる家になる。
これが私たちの目指す家づくりです。
⸻
■ 手仕事こそ、建築の「品」をつくる
美しい納まり、触れたときの質感、空間の張りつめ方。
どれも、図面だけでは到達できない世界です。
そこにあるのは、手仕事が生む品格。
そして、その家に住む人が自然と感じ取る
“心地よさの理由”だと考えています。
BUILD WORKs
代表取締役 河嶋 一志
